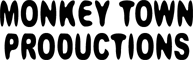「一度だけこの杖を投げ捨てて、おじいちゃんが旅に出たことがあるの」
引っ越しの日、押し入れから出てきたおじいちゃんの杖。わたしは、一番触れたくなかったおじいちゃんとわたしの最後の旅の話しを、彼に語りはじめた。
「おじいちゃんと孫娘が旅行に行ったのか」
”五十年間ニシンを待ち続けた男”という記事に興味を覚え、僕はその孫娘・春を取材し、老人と孫娘を題材にした映画のシナリオを書き始める。やがて春に強く惹かれていった僕は、
だがその愛ゆえに、映画の話を告げられずにいたー
第一章
わたしとおじいちゃんとの最初で最後の旅の話をしたいと思う。
それはわたしにとって初めての旅で、それまでのわたしは北海道の小さな町から出たことがなかった。
死んだお母さんからよく言われたものだ。「こんな町から、さっさと出ないとだめよ」って。
わたしには、その言葉の意味が、判らなかった。
「どうして?」
「世界は、広いの」
「広い…」
「そうよ。海のように広いの」
わたしたちの家の目の前に拡がる日本海の海しか見たことのないわたしだけれど、その言葉は、わたしに清々しさをもたらしてくれた。
「世界は、海のように広い」
わたしは何度もその言葉を自分に言い聞かせたものだ。
わたしは今、東京の中野区と言うところで暮らしている。
東京に来て三年。
浜川の「佐藤水産」と言う水産工場で働いていたわたしは、ある日社長の佐藤六助さんに呼ばれた。
わたしがかねてから東京で暮らしたいと言う希望をもっていて、佐藤六助さんもそれに賛同してくれた。
出入りの業者の人にことあるごとに話をしてくれて、鱈子の卸し先でもあった東京浅草の佃煮屋さんを紹介してくれたのだ。
引っ越しは簡単なものだった。
何せおじいちゃんが亡くなって、持ち出すようなものは何もなかったからだ。
わたしの持ち出した荷物は、数枚の下着と一張羅の母が作ってくれた赤いジャケット。それにわたしの大好きな本。林芙美子の「放浪記」。
それだけだった。
アパートを借りるお金は、佐藤六助さんが貸してくれた。
家賃は五万円。
小説「春との旅」より抜粋