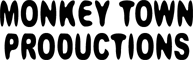著者:小林政広/A5版/311頁
2006年6月8日初版第1刷発行
発行:モンキータウンプロダクション/発売:キネマ旬報社
<あとがき> より
本文の三一五ページ「勇払にて③」から、三一九ページ「勇払にて⑤」をもう一度読み直してもらいたい。
著者が、北海道の勇払市にある北上荘という宿で一気に書き上げたという一冊の脚本のことが書いてあるだろう。
実は、この脚本は、もう私の手元にある。黒い表紙。銀文字のタイトル。強烈な内容だ。もちろん、撮影はまだ行われていない。
このホンを、ボクが目の前に突き出された時のことは、今もよく覚えている。
二〇〇五年の八月、北上荘。
そう、何だか知らないけれど、この小林政広という人は年じゅう北上荘にいるのだ。
その夏、石橋凌主演の「幸福」という映画を、小林政広監督はこの地で撮影していた。だいたい十日間ほどのシュート期間しかない低予算の小林組の撮影は中盤を過ぎた頃で、酒をあらかた断って久しい小林監督の、やることのない夜の時間を少しでも短く感じようと毎朝4時出発をスタッフに強いた彼の強固な姿勢にもようやく慣れ、その時も、次の日の早朝出発に備えて食堂を後にし、自室に戻ろうとしていた夜七時あたりだったように思う。
「これ、読んで下さい」
すでに、カロリーオフの発泡酒にちょっと口を付けただけで顔を真っ赤にしていた小林政広が、どこからか手にしてきた封筒を私の前に差し出した。
一年か二年に一本、という小林政広にしては珍しく、その時は、この「幸福」という映画を撮った直後に別の映画の制作が控えていたので、てっきりその台本かと思って封を切った。
違った。
黒い表紙。銀のタイトル。
それが、彼が本文中に記した、約一日で書き上げた脚本だった。
驚いて私は彼の顔を見上げた。赤ら顔のその奥で、よく見れば意外につぶらなその両の目が、異様にギラついていた。マジだ——私は思った。普段はふわふわと海中の藻のように揺れている小林政広の身体が、その時ばかりは全くと言っていいほど揺れていない。
「撮影は二〇〇六年の十二月です。全編、この北上荘で撮ります。その訳は、読んでもらえば分かると思います。で…これでパルムドール、狙いますから」
男は言った。
やれやれ。
北海道の端っこの苫小牧から一時間に一本の電車でようやく辿り着ける最果ての地・勇払の、飯と居心地だけは馬鹿にいいが、辺りは海外の地方都市のようにガランとして恐ろしく孤独な北上荘の一室で、小林政広は、カンヌで人生最大の勝負を賭けるための脚本を、しこしこ書いていたのだった。そして恥ずかしながら不肖私も、いつの間にか、何だか大きなその賭けの大いなる一端を担ぐことになってしまっていたのだった。
考えてみれば、この「幸福」という映画で、私はこの監督ともう四度も一緒に仕事をしている。その年の秋に、彼が生まれて初めて北海道以外の場所で撮影した最新作にも出演した。男が今まで仕上げた長編映画は都合九本だから、実に半分以上の作品に私は出させてもらっていることになる。思い起こせば、彼と初めて出会ったのは二〇〇〇年の暮れだった。
「歩く、人」という緒形拳主演の、ただ老人が北海道の雪景色の中を歩くだけの映画に年が明けてから参加するために、私は彼の事務所まで打ち合わせに出掛けていった。
脚本も書き、メガホンも取り、映画のセールスも自分でする、すなわち、一本の映画の全ての責任を取るという男の目の前に私は座った。
小林です。男は言った。
これが監督か。
しばらくは普通に話した、と思う。
何というか、小林政広という人は、一見気が弱そうで、口数も少なく、声もボソボソ言っているので、何を話しているのかよく分からない人だった。とどのつまり、何を考えているのかさっぱり分からない人だなあというのが、彼の第一印象であった。ちょうど、日曜の朝から東京ドーム横の馬券売り場の前で磨り減った赤えんぴつを耳に挟み、人生の終わりのような顔をしてヨレヨレの新聞をじっと凝視しているタイプの男だ。あるいは、コーヒーを十杯とワンカップを一ダース飲んで、それで一日があっと言う間に暮れていくような人間だ(こっちの方は当たっていなくもなかったが)。
また、撮影が行われた増毛という町は恐ろしく寒く、死ぬほど殺風景なゴーストタウンで、こんな死に絶えそうな町を好きこのんでやって来る監督もいるんだとほとほと感心した。
おまけに、映画の予算がとにかく少ない。なので本番は大抵一回だけしか回さない。録音部も記録さんもいない。大体、スタッフの数が、何だか区民会館で開かれるウイークデーの詩吟会に集まった近所の人たちくらいしかいないのだ。機材とかも、もちろんあまりない。休憩に出るはずのお弁当も、果たしてあったんだか無かったんだか。その中で、監督の「よーい、はい」という蚊の鳴くような小さい掛け声だけが、津々と雪の降りしきる裏日本の雪景色の中にこだまする。
ああ、もうこの人とは一緒に仕事をすることもお会いすることもないかもしれない。あまりの陰鬱な撮影の雰囲気に、私は確か、当時そう思ったように記憶している。
だが——そんな払っても払っても降り積もってくる数々のマイナス要素を足してもなお、この監督と厳冬の雪の中で過ごした時間が、東京に帰るとひどく懐かしくかけがえのないものに感じられたのは、なぜだろう?気弱そうで、口数の少ない、と言ったのはただの見かけだけで、その実、本当は我がままで意固地で頭の中では何百人もの人間をありとあらゆる手ひどい手段で切り刻んで殺戮している、この小林政広という隠れ擬似サイコと共に過ごしたたった一週間だかの時が、無性にしっとりと実のある、生きた実感を妙に味わえた、映画人として実に稀有な体験だったと、どうして思うに至ったのだろう?
その後、小林政広とは、この「歩く、人」がカンヌ映画祭の「ある視点」部門に出品されて、十日間も南仏で一緒に過ごすことになってしまった。当時、彼が行きつけの方南町の蕎麦屋で朝まで語り合ったこともあった。私は酔っていて記憶にないのだが、二〇〇三年の暮れに「フリック」という私自身のキャリアで初めての主演映画を彼に撮ってもらっている時には、私は彼に向かってついに心情を吐露し、「ボクの芝居は駄目ですか!駄目ですよね!いや、駄目なんだ!駄目に決まってる!うおおおおお」と滂沱の涙を流し泣きついたという。おまけに最近は、彼のことについて雑誌や何やらで平気で悪口を書けるようになってしまっている。
何だか分からないけれど、私はいつの間にか、小林政広というこの変わった人間を、何というか——随分と信じ切ってしまったようである。最初は、何だこの人、と思っていた寡黙な変人と、いつの間にやら腹の中で何かを共謀して共に企みをしている犯罪者同士のような心境になっている。
そして我々は、この本が出版される年の終わりには再び勇払の北上荘に籠もり、小林政広という人の人生にとって最も大きな賭けとなる共同作業へと突入しているのだ。
人生は、分からないものである。
ところが——である。
ここからが、実はこのあとがきの本題だ。
小林政広という人は、本文でも本人が口を酸っぱくして書いているように、糖尿病にかかっている。重度なのか、軽度なのかはご本人しか分からない。
「フリック」の撮影の前に発覚した糖尿の原因は、恐らくは、かつては飲めなかった酒を度重なるストレスから無理に飲むようになって、あっという間に酒量が上がっていったためであろうと推測される。
夕方に起きていきなりビール、次いで焼酎、で、朝までダラダラ飲み、酔い潰れてゴミのようになって帰宅、そして夕方に起きる。これを、映画監督になってからの小林政広は、撮影がない時はずっと繰り返していた。彼の口からはそう聞いている。
そして糖尿病の発病以降は——食事制限、禁酒、早起き、全ての天地がひっくり返るほどの生活を今度は自らに強いねばならなかった。彼と会っても、食事は出されたものをまあ三割程度、それよりもその後、鞄の中からその十倍くらいの量はあろうかという錠剤をじゃらじゃら出して口に放り込む。徹夜明けの漫画家のような、彼本来のげっそりした外見と、この、百錠くらいありそうな錠剤を不味そうに飲み込む姿とが、何とマッチしていることか——とは口が裂けても言えなかったが、とにかく彼は、それまでの態度を改めることになる。
一年が過ぎ、やがて二年が過ぎた。
ウサギのような生活が続いた。彼の楽しみは、もうタバコだけ——あとは自分の映画を撮りに北海道に行くだけ——それと、少しの他人の悪口——しかし、転機は、間もなくやって来た。
また、カンヌだった。
二〇〇四年の終わりに撮影した「バッシング」が、カンヌのコンペ部門に入ったのだ。ずっと、ずっと彼が願っている数少ない望みのうちの一つが、いきなり彼の人生に降りかかって来たのだ。
飲まずにはいられない。
飲ますにはいられない。
飲まずにはいられない。
酒が、また少しずつ彼の身体に忍び寄り出すまでに、そうは時間はかからなかった。
そのことは、本文にも本人の口から詳しく述べられているのだが、精神的には以前とは比べものにならないほど苦しい材料が減っている状況のおかげで、立派な糖尿病とはいえ、小林政広の健康状態は、現在、奇跡的に良好なレベルを保っている。とはいえやはり、彼が糖尿病患者であることに変わりはない。状況が良好だけに本人の気が大きくなって、夜ごとの酒が急ピッチで増量されている事実も無視できないだろう。
だから私は、声を大にして言うのである。
あなたがこれを読む頃、小林政広は、死んでいる。
いや、間違った。
小林政広は、死んでいるかもしれない。そう、死んでいるかもしれないのだ
よって、彼がどんな些細な悪口や罵詈雑言や妬み、嫉みを書き連ねたところで、それは病人の戯言だと思って許さねばならない。この日記のある日の文章の九割が、自分がタバコが吸えなかったのは誰々のせいで、そんなおまえは死んじまえ馬鹿野郎云々しかじかと恨み辛みで塗り固められていたとしても、それを決して責めてはいけない。
遺言なのだ。全て。
だから私も応援する。
ましてや我々には、どうしても今年、北上荘で仕上げねばならない大仕事が待ち構えている。今、この痩身の糖尿病患者の病を、全うさせる訳にはいかないのだ。大好きな芋焼酎飲んで、はい、さよなら、と天国に(あ、地獄か)突き出す訳には絶対にいかないのだ。
あなたには、分かるまい。
この本を最初から最後まで熟読したところで、あなたには、小林政広という人が、何かどうしても肩を支えて後ろからそっと助けてあげたくなってしまう魅力を備えた、愛すべき不完全さと不器用さに貫かれた男だとは、決して分かるまい。
阪神タイガースが、大阪の民衆の訳の分からぬ善意と好意でがっちりと支えられているように、小林政広という男もまた、ある種の変わった人間たちの度を超した友情と熱意によって、多分、大きく支えられているのである。
私には、ひとつ、思っていることがある。決意していることがある。どうしても、やってみたいことがある。
彼の目が黒いうちに、絶対に彼とカンヌの赤絨毯の上を歩き、映画祭の最後の表彰式の日に、大会場のサル・リュミエールの壇上に彼を乗っけ、彼を感涙にむせびさせる。そしてシャンパンを彼の頭にしこたまかけ、シャンパンに溺死しながら、クロワゼット大通りを彼と朝まで歩く。ホテルに帰る。まだ人もまばらなロビーで、固い握手をする。そして言うのだ。もう、どれだけ飲んでもいいですよ、監督、と。
それまでは、彼を逝かせる訳には、絶対にいかない。
行き場のない思いをペンに綴り、やり場のない怒りを溜め込み、過去の自分と今のおのれを冷ややかに見つめ、未来の自分に失望し、糖尿病の数値を子細に眺めたり、一日のカロリーを計算したり、その日飲んだ焼酎の杯数を頭の中に並べたり、もうあなたはじゅうぶん、やってきたじゃないですか。
もう、いいじゃないですか。
彼のことだから、巨匠監督のように達観して、何でも「はいはいいいですよ」と言って丸くなってしまうことはないと思うけれど、そろそろ、身を削って血を売るような痛い思いはもうしなくてもいいよ、監督。映画の神様からミラクルを戴いてもいい頃だよ、監督。
待ってろ、小林政広。
私のような四十の中年が五十のおっさんに言うことでもないが、この際もう言ってしまおう。
私たちが、あなたを男にする。男にする。
男に。
待ってろ、小林政広。
二〇〇六年 三月
香川照之