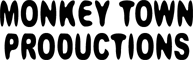Director’s Statement
この映画の元になったシナリオは、『バッシング』が出品された2005年のカンヌ映画祭の、直後に書かれたものです。「原罪」( original sin )という言葉が脳裏をかすめ、昔読んだソルジェニツィンの「イワン・デニーソヴィッチの一日」(One Day in the Life of Ivan Denisovich)の事が思い出されました。(劇中で、主人公が愛読している本として取り上げました)殺人事件の被害者の親と加害者の親が、収容所の様な閉じられた場所で、偶然出会い、再生への道を歩んでゆく―。
『バッシング』が贖宥(しょくゆう=indulgence)の物語ならば、『愛の予感』は、その後に来る再生(rebirth)の物語です。
小林政広 2007年
脚本・監督:小林政広
音楽:小林政広
撮影監督:西久保弘一
照明:南園智男
録音:秋元大輔
編集:金子尚樹
助監督:川瀬準也
男(桂木順一):小林政広
女(木内典子):渡辺真起子
2006年12月 北海道苫小牧市
2007年11月
愛の予感 予感から再生へ
秦 早穂子
人は失ってしまった心をどんな風に取り戻し、蘇らせていくのだろう。監督小林政広は、独自の映像言語で主題に迫っていく。
14歳のひとり娘を同級生に殺された父。すでに妻を癌で失くし、彼はひとりになってしまった。母子家庭とはいえ、普通の暮らしをしていると思っていた母。娘が突然、友だちを殺したー。
こうした事件は、日本のどこかで、かたちを変えながら、数を増している。映画は、この父、この母の、その後を追う。
新聞社を辞めた父は、北海道のある鉄工所で肉体労働者になった。食べる、働く、眠るだけの毎日。
殺人者の娘を持つ母は、生まれ故郷の北海道に戻り、更に知らぬ町へと流れて、下宿北上荘で、通いの賄いの職を得た。決して許せない、償い切れない過去の重荷を背負ったふたりが、行き着いた所は、図らずも同じ宿だった。
社会状況、日常の夾雑物、他者の介入を排除し、会話、音楽すらない。今や人間を支配する携帯電話も棄てられる。ふたりの後姿をカメラが執拗に見つめるだけだ。いつも同じような映像と音の繰り返し。溶鉱炉の火を吐く音。車の発車音。廊下をするスリッパ、又は馬鈴薯の皮を剥く、卵を割る、フライパンに油の跳ねる音。
あの父と、あの母は、毎日、同じパターンの行動のなかで、いつから、ひとりの男、ひとりの女として存在し始めたのだろう?ふたりの仕草から変化を発見するのは不可能だし、まして彼らの心の内が判るはずもない。ゼロ地点で息を殺した男と女の、それぞれの日常を、見る側はうんざりするほど突き付けられる。見えてくるのは、働く男。食事する男。彼は下宿で、朝晩、飯、味噌汁、生卵だけを食べ続ける。主菜は手つかずのまま。それをじっと窺っている女。
一日の仕事を終え、ひと風呂浴びようと、ズボンのジッパーを下げる。その音。肉体は意外にがっちりしている冴えない中年男は、自分の顔を取り戻し始めた。そして、ある日、杓文字に一杯の味噌汁が二杯になる。別の日は、主菜に手をのばし、又の日、生卵の代わりに、女が作った目玉焼きを口にする。
初めのうちは黒眼鏡をかけ、前髪でかくされた女の顔は全く見えない。自分の顔がない女は、娘のことも理解できず、自分のことも判らない。朝の仕事が一段落すると、女はコンビニで昼食用のサンドイッチとパックの飲み物を買い、アパートに戻る。夜は北上荘の流し場での立ち食い。その後ろ姿に新香を噛む音をかぶせる。
小林政広の描く女は、しばしば無愛想で不快でさえある。心理分析をせず、解釈を与えず、実存そのままの女を放り出してくるからだ。自分の心も掴めず、表現できない女は、男を殴る。この辺りから、女の顔が見えてくる。カリカリ新香を噛む音が、なぜか、なまなましい。
被害者と加害者の立場を超えて、男と女として互いを意識し始めると、反復されてきた画面がぎごちなく動き出す。すべては、この予感をつかむための過程だったのだ。人生に、一度か二度、必ずやってくる予感。そこにはエロティックな匂いさえ漂う。エロス、つまり、生の本能が持つエネルギーが再生のきざしを暗示する。
過去の痛みから浮上して、愛に至るかもしれない男と女の、今日から明日につなぐ、一瞬の感情のきらめき。映画の常道をぶち破って、ささくれた日常のなか、取り戻したい心を、小林政広は過激に一気に叩きつける。
ロカルノ映画祭と映画監督小林政広
市山尚三 東京FILMeXプログラムディレクター
仕事柄これまで様々な国際映画祭に参加したが、「最も好きな映画祭はどこですか?」という質問には、必ず「ロカルノ映画祭です」と答えるようにしている。このロカルノ映画祭、日本ではそれほど馴染みがあるとは言えない。1998年に清水浩監督の『生きない』が上映された時は、脚本兼主演のダンカンがロカルノに参加したこともあり、一部で大きく報道されたが、それ以降(あるいは、それ以前から)、コンスタントに日本映画が上映されているにも関わらず、ロカルノ映画祭が大きくクローズアップされることはなかった。ロカルノはカンヌやヴェネチアのように派手なハリウッド・スターが顔を見せる映画祭ではなく、そのため日本のプレスが積極的に参加していないことが日本での知名度に響いていることは間違いない。その一方、ヨーロッパの映画界では、ロカルノ映画祭の公式上映作品に選ばれることはアート映画界において大きな価値を持つものと見なされている。昨年の例で言えば、ドイツ映画『善き人のためのソナタ』(監督:フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク)がロカルノ映画祭でプレミア上映され、観客賞を受賞した後、昨年の全てのヨーロッパ映画を対象とした「ヨーロッパ映画賞」の最優秀作品賞に選ばれたことがそのことを端的に語っている。カンヌやヴェネチアのような巨大な映画祭では埋もれてしまいかねない作品が、ロカルノで上映されることで大きくクローズアップされ、その後の評価や興行成績に結びつくことは決して少なくはない。
ところで、筆者がロカルノ映画祭を最も好きな映画祭としている理由は幾つかある。一つはこの映画祭の雰囲気。アルプスの山中、マッジョーレ湖に面した小都市ロカルノは、古き良きヨーロッパを思わせる閑静な街で、カンヌのような喧騒とは無縁だ。もちろん、映画祭にはヨーロッパの配給業者なども多く参加しているのだが、バカンスの真最中である8月上旬に開催されるからか、どの業者もリラックスしており、ギスギスしたところがない。とりわけ、街の広場ピアッツァ・グランデで毎晩行われる野外上映は、映写状態の良さも含め、他の映画祭にはない素晴しい雰囲気を味わわせてくれる。もう一つは、この映画祭が新しい才能の発見の場であることだ。特に、1991年に現ヴェネチア映画祭ディレクターのマルコ・ミュレールがディレクターに就任した後は、著名監督の作品を意識的に回避し、先鋭的な若手映画作家の発見の場というステータスを確立した。そしてその方向性は現ディレクターのフレデリック・メールが昨年就任した後も継続されている。
小林政広監督の『愛の予感』がロカルノ映画祭のコンペティションに選ばれ、見事金豹賞を受賞したということは、このようなロカルノ映画祭の性格を考えると非常に興味深い。小林監督は年齢の面でも作品歴の面でも(例えば『バッシング』でカンヌ映画祭コンペティションの実績がある、ということからも)新進作家とは言い難い。それにも関わらず『愛の予感』がコンペティションに選ばれたことは、映画祭側がいかにこの作品を先鋭的と見なしたかを意味している。実際、登場人物も場面設定も極めて限定されている『愛の予感』は、小林監督のこれまでの作品の中でも最も先鋭的であると言って間違いないだろう。そして、この作品を評価して金豹賞を授与した審査員団もまた、先鋭的であったと言えよう。
筆者にとって悔いが残るのは、何度となくロカルノ映画祭に参加していながら、今年に限って行かなかったことである。『女理髪師の恋』がスペシャル・メンションとして表彰された時には、ピアッツァ・グランデのステージで控えめにフランス語で謝辞を述べる小林監督の姿を拝見した。金豹賞を受賞した小林監督は何と言ったのだろうか。残念ながら、歴史的瞬間を見逃してしまった。
驚きとともに
大久保賢一 評論家
男と女の無言のやり取りを見続けていて、チャップリンとキートンの競演を連想した。実際に彼らが競演した「ライムライト」ではなく、もっと以前の、全身の動きのみで輝いていた二人がやりあっているような、ありえない競演のサイレント映画を夢想してしまったのだ。
人間の滑稽さというものを引き受けるという意味ではこの「愛の予感」は人間喜劇といってもいいのかもしれない。だが、それ以上に、ここで、男と女が言葉を発することなく、まずは世界に対して逃走という必至の抵抗を試み、次いでそれを放擲していくという経過を、その身体の表情のみで表すというかなりラジカルな方法がサイレント・スラップスティックの作品の美しさを連想させたのだ。
起きてしまった出来事について、そのことで日常を破壊されてしまった男と女が語る。「こと」について言葉による説明が行われるのはこの冒頭だけだ。
二人にそれを語らせる「聞き手」の声は、二人をつなぐ役割も演じているようだが、ニュートラルではなく、「世間」を代表するものだろう。
男と女、それぞれの娘について、そのあとは幕切れでもういちど冒頭に戻る(二人それぞれの、二様の顔が対比される)まで一切、語られることはない。
そのことだけでなく、このあと「一年後 苫小牧 勇払」とされる時と場所では、一切、言葉は封じられる。
その文字が出て、いきなり巨大な炎。溶鉱炉の炎を包む空間。その量感あふれる画面が、シンプルな労働の手順をみせながら、このあとも繰り返し現れる。毎日毎日がその作業の正確な繰り返しであるということ。男が望んでいた「何も考えず、体を使って働く」という状況。
男は就寝前に文庫本を開いたりもする。そして寝具と小さなテーブルしかない部屋の、そのテーブルの上にある文庫本はドストエフスキーの作品かもしれないが、しかし、読むことが何かをもたらすことはない。
溶鉱炉の現場で男たちは防護マスクを着用している。それぞれの顔が示されることはない。合図以外の言葉もない。ただ正確に作業が進められる。
それは賄いつきの宿舎でも同じだ。食堂では誰も言葉を交わすことなく食事を終える。男は風呂に入るのも一人だ。
男が食事をとる様が正面から映される。ストーン・フェイス。女の賄いの労働。彼女は終始うつむいている。食事も調理も一切、快楽ではなく、ただ時間を埋め、経過させるための労働として、寡黙なアクションとして演じられる。後段で、コンビニで買われたプリペイドの携帯電話が両者の間で「突っ返し」の繰り返しを見せるようになるまでは、食べること、調理することは溶鉱炉の労働に等しい。
しかし、快楽であれ、労働であれ、それが映画のアクションとして成立せず説明に終わる作品が山ほどあるなかで、この作品での食事をめぐっての(向かい合う以前の)二人のアクションの応酬には目を奪われる
食べる(ほとんど生卵を飯にかけるだけの)男の正面のショット、お茶を入れにいくやせた体、一方の女はフライパンに卵をとく動き、男たちが食べ終わってから立ったまま飯をかきこむ背中、夜のアパートまで体をすぼめて戻る足取り。我々は彼女の顔以外を見つめ続けることになる。
この作品は、彼女の顔が正面から見られるまでのドラマだ。そうすることが男にできるようになるまでのドラマであり、彼女の感情がやみくもに突き出されてくるその唐突さを、我々が驚きとともに受けとめるという体験をする映画なのだ。そのスリルとサスペンスこそ、映画の醍醐味といえないだろうか。
「愛の予感」パンフレットより

「愛の予感」撮影現場 清水製鋼にて 主演 小林政広