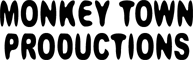評論家
大久保賢一
男と女の無言のやり取りを見続けていて、チャップリンとキートンの競演を連想した。実際に彼らが競演した「ライムライト」ではなく、もっと以前の、全身の動きのみで輝いていた二人がやりあっているような、ありえない競演のサイレント映画を夢想してしまったのだ。
人間の滑稽さというものを引き受けるという意味ではこの「愛の予感」は人間喜劇といってもいいのかもしれない。だが、それ以上に、ここで、男と女が言葉を発することなく、まずは世界に対して逃走という必至の抵抗を試み、次いでそれを放擲していくという経過を、その身体の表情のみで表すというかなりラジカルな方法がサイレント・スラップスティックの作品の美しさを連想させたのだ。
起きてしまった出来事について、そのことで日常を破壊されてしまった男と女が語る。「こと」について言葉による説明が行われるのはこの冒頭だけだ。
二人にそれを語らせる「聞き手」の声は、二人をつなぐ役割も演じているようだが、ニュートラルではなく、「世間」を代表するものだろう。
男と女、それぞれの娘について、そのあとは幕切れでもういちど冒頭に戻る(二人それぞれの、二様の顔が対比される)まで一切、語られることはない。
そのことだけでなく、このあと「一年後 苫小牧 勇払」とされる時と場所では、一切、言葉は封じられる。
その文字が出て、いきなり巨大な炎。溶鉱炉の炎を包む空間。その量感あふれる画面が、シンプルな労働の手順をみせながら、このあとも繰り返し現れる。毎日毎日がその作業の正確な繰り返しであるということ。男が望んでいた「何も考えず、体を使って働く」という状況。
男は就寝前に文庫本を開いたりもする。そして寝具と小さなテーブルしかない部屋の、そのテーブルの上にある文庫本はドストエフスキーの作品かもしれないが、しかし、読むことが何かをもたらすことはない。
溶鉱炉の現場で男たちは防護マスクを着用している。それぞれの顔が示されることはない。合図以外の言葉もない。ただ正確に作業が進められる。
それは賄いつきの宿舎でも同じだ。食堂では誰も言葉を交わすことなく食事を終える。男は風呂に入るのも一人だ。
男が食事をとる様が正面から映される。ストーン・フェイス。女の賄いの労働。彼女は終始うつむいている。食事も調理も一切、快楽ではなく、ただ時間を埋め、経過させるための労働として、寡黙なアクションとして演じられる。後段で、コンビニで買われたプリペイドの携帯電話が両者の間で「突っ返し」の繰り返しを見せるようになるまでは、食べること、調理することは溶鉱炉の労働に等しい。
しかし、快楽であれ、労働であれ、それが映画のアクションとして成立せず説明に終わる作品が山ほどあるなかで、この作品での食事をめぐっての(向かい合う以前の)二人のアクションの応酬には目を奪われる
食べる(ほとんど生卵を飯にかけるだけの)男の正面のショット、お茶を入れにいくやせた体、一方の女はフライパンに卵をとく動き、男たちが食べ終わってから立ったまま飯をかきこむ背中、夜のアパートまで体をすぼめて戻る足取り。我々は彼女の顔以外を見つめ続けることになる。
この作品は、彼女の顔が正面から見られるまでのドラマだ。そうすることが男にできるようになるまでのドラマであり、彼女の感情がやみくもに突き出されてくるその唐突さを、我々が驚きとともに受けとめるという体験をする映画なのだ。そのスリルとサスペンスこそ、映画の醍醐味といえないだろうか。
「愛の予感」パンフレットより