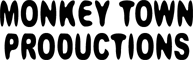Director’s Statement
今、日本では、様々な人へのバッシングが、はびこっています。長い不況で、町に、失業者が溢れ、誰もが、自分自身への不安を抱えている今日、そのストレスが、他者への、バッシングとしてあらわれているのだと思われます。この映画は、北海道のとある町で起こった、ひとりの女性へのバッシングを描いたフィクションです。この映画は、痛烈に、現代日本を批判すると共に、親子のあり方を問う、普遍的ドラマでもあります。 主人公有子は、いつか来るかも知れない、あなたであり、私なのです。
小林政広
脚本・監督:小林政広
撮影:斉藤幸一
照明:花村也寸志
録音:秋元大輔
編集:金子尚樹
助監督:川瀬準也
制作:板橋和志
有子:占部房子
孝司:田中隆三
岩井:加藤隆之
植木:本多菊次朗
典子:大塚寧々
井出:香川照之
撮影:2004年10月 北海道苫小牧市
公開:2006年6月
ファジル国際映画祭における『バッシング』
市山尚三 東京フィルメックス プログラム・ディレクター
今年の1月20日から30日までイランの首都テヘランで開催された第24回ファジル国際映画祭で『バッシング』は準グランプリに相当する審査員特別賞を受賞した。約300本もの映画が上映されるこのイラン最大の映画祭に、筆者は国際コンペティション部門の審査員として参加した。審査員長は『ブリキの太鼓』でカンヌ映画祭パルム・ドールを受賞したドイツの巨匠フォルカー・シュレンドルフ。他の審査員はアイスランドを代表する映画作家フリドリク・フリドリクソン、イランと日本の共同製作映画『風の絨毯』を監督したカマル・タブリーズィーらで、総勢6人。コンペ対象作品17本にはカンヌ映画祭で監督賞を受賞した『隠された記憶』、ヴェネチア映画祭で2冠を獲得したジョージ・クルーニー監督作品『グッドナイト&グッドラック』、日本でも昨年公開された話題作『ヒトラー〜最後の12日間〜』など、錚々たる作品が並んでいる。
実を言うと、最初はこの強力なラインアップの中で『バッシング』が審査員たちにどう評価されるのか不安な点もあったが、審査委員会が始まるとそれは杞憂に終わった。全ての審査員が『バッシング』に高評価を与えたのである。しかも、その評価は題材やテーマ性というよりも、むしろ監督の演出、ストーリー構成、俳優の演技などに向けられていた。「映画を見てゆくにつれ、誰かが突然画面の外から現れてこのヒロインを攻撃するのではないか、という思いにとらわれ続けた」とシュレンドルフは筆者に語ったが、これは小林監督の演出力に対する最大級の賛辞であろう。社会問題を扱った映画が受賞した時、しばしば「あのような題材だったから評価された」などと言われることがあるが(そして、そういうこともあるとは思うが)、この『バッシング』の受賞については、明確に映画それ自体の力が評価されたと言える。
もっとも、審査委員会を離れた場で、筆者は何人かの審査員に対し「なぜこんなことが起こったのか?」という疑問に答えねばならなかった。興味深かったのは、シュレンドルフによると、昨年11月にやはりイラクで武装勢力の人質になったドイツ人女性が、解放された後に「またイラクに戻りたい」と語ったと報道され、マスコミによるバッシングが起こったという。ドイツでの状況は詳しくは知らないが、このような話を聞くと、この映画で描かれたような”バッシング”は日本だから起こったのではなく、世界のどこででも起こり得ることのように思える。その意味では、この映画を実際に起こった事件の再現というよりは、社会から疎外されるヒロインに絞って映画化した小林監督の判断は極めて正しかったと言えるのではないだろうか。
「バッシング」パンフレットより
彼女は本当に「異物」なのか
阿部嘉昭 評論家
04年、イラクを舞台に起こった日本人人質事件をモデルにしたこの『バッシング』が社会派映画に属するのは当然だ。だが作品には社会性が不足しているのではないか——最初そうおもった。善悪の区分が複雑化した現在、多様な角度から複数の問いを発し、一元的な回答を観客に導かない配慮が、社会派映画には必要。ところが本作では解放された人質に向けられた他者(家人を除く)の反応が拒絶感一色だし、小林政広監督自身も、ヒロインへの観客の印象をより複雑にする、事件のTV報道の描写を禁欲してしまっている。だから作品がヒロイン有子(占部房子)への違和感しか導かない——そう捉えた。 整理しておこう。国が保証した「非戦闘地域」でボランティアに励んだ日本人がイラクのテロリスト集団に拉致されたとき、最初だけ「人命尊重」の世論が走った。以後は「自己責任」論に反転する。幼稚な世界認識によって迷惑をかけた者の身代金を「我々の税金」でまかなう必要はない——人質は自ら死ぬ責任を負えと。この「自己責任」がネオリベラリズムの用語だという点に注意しよう。世界を支配するアメリカイズムの一端がネオリベラリズムだった。「小さな政府」は国民のセキュリティのみを守る。国民は幸福も利益も自由に——ただし自分の責任内で、追求してよい。この「セキュリティのみ」という限定が実は厄介で、これがやがて「異物」の発見ゲームを導く。当時の「自己責任」論は一面でそれを機会的・遊戯的に展開したにすぎなかった。この作品はこうした危険な世相変化に対しても態度を鮮明にしていない。 ところが観終えて鮮烈に迫る何かがある。占部の存在感が作品を振り返るごとに増してくる。しかも小林監督が社会性を見事に盛りえたという逆の感想ももたげてくる。その印象変化の最初のきっかけが、占部がコンビニ店員に「つゆたっぷり」「具材ごとに分けて」盛ってと要請したおでんを考えたことだった。店員や、つゆが不足し他の客にも迷惑をかけるかもしれない点で、あの注文法は明らかに配慮を欠く。眼前の世界への配慮を欠くボランティアはいくらイラクで歓迎されようと独善のそしりを受ける。この点に作品が確信的だった。店員からおでんの販売を「父殺し」を理由に拒否されたとき占部は代わりにマクドナルドの商品を買って帰る。「親イラク」の足元が崩れている。(裏面へ続く) 彼女は「自己の運用」を間違えているのだ。そう捉えると、嗚咽・笑みが正しいタイミングからズレたり、誤用されたりする彼女の魯鈍さ・痛ましさにも別の感慨が湧く。監督は彼女が「本当に異物なのか」を問いかけている。失敗ばかりの人生、自分の有用性を唯一確認できるボランティアへの情熱。そこに賭けるしかない彼女を社会的に——同時に「女として」見つめる視線が一貫していた(しかもヒロインは最後に正しい嗚咽と笑みを通じ表情回復までする)。これは観客の他者洞察自体を問う厳格な作品だった。それに応えた占部の演技、その静かな持続感と集中もまた、見事極まりなかった。 瀬々敬久や佐野和宏作品での活躍で知られるカメラマン斉藤幸一と小林監督との緊密な協働態勢が、作品の厳しさには必須だった。対象の動きに感応しつつ、非人称の位置から生成的に視界を開いてゆく斉藤のカメラ。それが編集・金子尚樹の刻む呼吸と相俟って、苫小牧近郊(とくに団地)の荒涼とした質感を、霊的な高みにまで定着してゆく。ヒロインの父役・田中隆三の自死を予告するくだり。ヒロインが帰宅すると父は不在だった。窓辺のカーテンだけが微風に揺れている。彼女が窓を閉めるとき斉藤はベランダから部屋に向けカメラを構える。閉められるに従い、窓に海が映る。一呼吸置き、斉藤のカメラは海側にゆっくりパンする。荒々しい波が打つテトラポッド。そうして父の自殺が暗示された。 自死の痕跡として揺れるカーテンは『やさしい女』の引用ではないか。ロベール・ブレッソンがドミニク・サンダの無表情の謎を追ったように、小林監督も占部房子の表情のズレの悲哀を追った。そうしてカッティングの質はちがうが『やさしい女』同様の峻厳に達した。そういえば小林監督はサトウトシキ作品の脚本から自らの監督作まで、自分の映画狂の資質の処理に苦慮してきたとおもう。「ジャンル映画」「映画であることを自己言及する映画」「数学的な遊戯映画」「演劇的な重さをもつ映画」——。従来作のジグザグの川筋は、この作品で一つの海に注ぐ。現れたのは「飲み込むには辛い」「だからこそ飲み込むべき」他者の姿だ。最初に海が出現したときは衝撃が走るが、冒頭の黒画面で流れていた海鳴りの音も、イラクにあふれていただろう戦闘音を想わせた。ヒロインの存在が記憶につよく迫るように——ヒロインの団地が海風で腐蝕されているように——作品自体もまた観客に対し侵食的であること。こうした作品の「立ち方」、その迫力が素晴らしかった。
「バッシング」パンフレットより

カンヌ映画祭2005 オフィシャルポスター